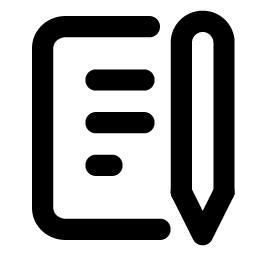家庭教師の作り話です。
家庭教師派遣業社からの依頼だった。
傷害事件を起こして補導されて高校を中退したAという少年を任された。
中退後、親の転勤で離れた町へ引っ越し、予備校に通い高校への再入学を目指した。
しかしそこで知り合った仲間とゲームセンターに入りびたりになった。
全く受験生としての生活をしないので元々住んでいた地域の親戚に預けられた。
その親戚は商売をしていて家には駐車場があるがそこに車を置かずに五分ほど歩いた公的な駐車場に車を止める様に指示された。
小学生の息子に影響しないように訪問は平日の昼間のみにする様にも指示された。
この親戚の申し出を見ればAがいかにその家から煙たがられているのかがわかる。
夏の暑い日、はじめてAの家を訪問した。
玄関のベルを鳴らしてドアを開ける。
たいていは家の大人が出てくるものだが、そこにはAが1人で立っていた。
痩せて少し背が高い。
髪の毛は茶髪で少しパーマをかけているようだ。
真っ赤なパンツ姿で上目づかいでこちらをにらんでいる。
何も言わずに奥に入っていくので私も後に続く。
大人は誰もいない。
広くて立派な座敷に彼は座ってじっとこちらを見ている。
「はじめまして、家庭教師の吉田です。」
そう言うと少し首を動かした。
しかし何も言わずにずっとこちらをにらみつける様に見ている。
どこか怯えたような緊張した様子でこちらを見ている。
私も何も言わずにじっと彼を見ていた。
わずか数秒だったと思うがとても長い時間に思えた。
Aもじっとこちらを見ていた。
彼がふと目をそらした。
私はその瞬間を見逃さずに言葉を発した。
「俺の事を殴るなよ。」
彼は驚いたようにこちらを見て言った。
「え?」
「俺は勉強を教えに来ただけだから嫌だったら帰るから俺の事を殴るなよ。」
何故かAは少しほっとしたような表情になって言った。
「そんなことはしません。」
「でもめっちゃ殴ってきそうな感じやん」
このやり取りだけでAとは仲良くなった。
学校へ行く途中で他校生とけんかになってたまたま相手が怪我をして退学になった。
小さい頃から塾に行っていて勉強は苦手ではなかったが大嫌いだった。
父親が嫌いだ、とも言った。
嫌いな理由として一つのエピソードを語ってくれた。
小さい頃から沢山の習い事をさせられていてその一つがスイミングだった。
ある大会で2位に入ったことがあった。
初めて手にした賞状を嬉しさいっぱいで父親に見せた。
褒めてくれると思った父親はこう言った。
「どうして一番じゃないんだ。」
Aと勉強を始めて何度かしても家の大人を見かけることは無かった。
家の一階がお店なのでそこには誰かがいるようだ。
Aはその親戚の家族とはほとんど話をしないらしい。小学生のいとことも話さないらしい。
中学の同級生が沢山近くに住んでいるが退学したいきさつもあり連絡を取ってはいないそうだ。
突然Aの電話が鳴り今から父親がやってくるとのことだった。
Aは父親が来る事をとても嫌がっていた。
公務員だという父親はきちんとした身なりだった。
「こちらの事務所にたまたま用事が出来たのでご挨拶に来ました。」
言葉使いは丁寧だが、表情は硬くどこかこちらを見下している様な印象だ。
「息子はどうですか?」
「キチンと頑張ってやっていますよ。」
「そういうことではなくてどこの高校に入れそうですか?」
「まだ始めたばかりなのでそれは解りません。」
「家庭教師の先生なら模試かなんかをして判定できないですか?」
「やってもいいですけど、今模試をやってもきっとどこにも行けないという結果しか出ませんよ。」
「これからどれだけ頑張れるかが全てです。」
私のその言葉に父親は表情を曇らせて簡単な挨拶をして去って行った。
父親はいつもはもっと偉そうに自分の意見を押し通す。その父親がおとなしく帰ったのが凄い、と言ってAはなぜかとても喜んでいた。
そんなことで褒められても困る。
ある日普段通りにAを訪問したが、彼はいなかった。家の中には誰もいないようだった。
一階の店に入ってみた。
そこには一人の女性がいた。
よくAが言っていたおばさんなのかもしれない。
事情を話している途中、彼女はほとんど何も言わずに私を店の外に促した。
一台の軽トラがとまっていて中から年配の女性がおりてきた。
「先生ですか。Aがお世話になります。こちらにおりますのでどうぞ。」
自分はAの祖母でAはその親戚の家とケンカをして近くの自分の家にいるのでそちらに来て欲しいとのことだった。
少し歩いて着いた祖母の家にAはいた。
いつもと変わった様子は特になかった。
早速勉強を始めようと思ったのだが、何故か祖母が席を離れない。
祖母のものの言い方に一抹の不安を覚えた。
元々は自分たち夫婦が商売をしていた。
それを娘夫婦に譲った。それがAがいた親戚の家の様だ。
Aの父親は長男だが勉強が出来たので家を継がずに公務員になった。
祖母は自分の息子と娘の話をしているのだが、そこには悪口に近いものを感じる。
息子も娘も口が悪く、自分中心で人の事を思いやる気持ちが無い、それでAがかわいそうだという事らしい。
年配の方なので私に対しての配慮が過ぎてそう言っているのかもしれない。
祖母の家での勉強がしばらく続いた。
Aはなかなか優秀だ。
宿題を出してもきちんとやってくる。
「暇だから、、」
照れながらそう言うが今の状況から抜け出したいという思いが強いようだ。
もしかすると小さい頃から父親のしていたことの効果なのかもしれない。
「今だったら、○○高校に行けるかな?」
「何点取ったら△△高校には行けるかな?」
前向きな発言が多く、父親や親せきに対しての恨みのようなことは言わなくなった。
そのため私も祖母の家での生活がどうなのかを聞くことをしなかった。
祖母を見かけることもなかった。狭い家なので勉強中は気を使って留守にしている様にも思えた。
願書を出すか出さないかという時期のある日だった。
派遣業者の担当者からだった。
「A君のお父さんから連絡があって家庭教師を終了にしたいとのことです。今住んでいるおばあさんとケンカをして家を飛び出し、今は父親の家に戻っているそうです。」
Aと直接連絡を取る手段がなかった私には何もできなかった。
その年の高校入試の出願状況が発表になった時、学区移動という欄に1という数字が載っていた。
きっとそれがAだったのだろう。
もしかしたら今頃はAも父親になっているかもしれない。
優しい父親になってるいことを願うばかりだ。
あの父親もきっと定年を迎えただろう。
良いおじいちゃんになっていることを願うばかりだ。
あの祖母はどうしているだろう、、、
2月24日
学校のストーブの周りに集まってけだるい時間を過ごしていた。
学校での主導権は下級生に譲ってしまっていた。
部活が終わり、生徒会が終わり、恋も終わり、友人関係も終わり、
まるで青春が終わったような寂しさを感じていた。
目の前に迫った受験や別れに怯える日々を過ごしていた。
いつも同じメンバーで集まっていたので会話が弾むことさえなかった。
「最近、酒田さん(仮名)が可愛くなったんちゃう?」
誰かがそう言った。
酒田さんはクラスの女子生徒で、真面目で大人しくあまり目立つ存在ではなかった。
私は話した記憶さえもない。特別美人ということもなく、意識をしたことの無い生徒だった。
「誰かに恋でもしてるんとちゃうん?」
しばらくしてから俺がそう言ったもののそれに突っ込んでくる奴はいなかった。
「誰やろ?」
そんな詮索に発展することもなく、また無言のけだるい時間が流れた。
2月になり、登校する機会がなくなったある日、学校からの連絡網が来た。
「酒田さんのお父さんが亡くなり葬儀に参列するので14日に集まるように、」
バレンタインデーだったがワクワクするような予定もなく、参列する予定を受け入れた。
酒田さんの家は住宅街にある小さなお好み焼き屋をやっていた。
食べに行ったことは無かったが家の場所は知っていた。
当日はクラスのほとんどが集まったが、同窓会の様な盛り上がりはもちろん無かった。
我が事の様な悲しさもまた感じなく、そのことに違和感を覚えた。あれから長い時間がたったが参列したときのことはよく覚えている。
周りの人にしきりに頭を下げるお母さん、遺影を持ってうなだれる酒田さん、泣きじゃくる小学生の弟の3人の姿だ。
その当時は父親が亡くなるなんて考えられなかったのだが、遺された家族の姿を見て何とも言えない暗くて辛い気持ちになった。
同級生との会話をいくらもしないまま式が終わると家に帰った。
その10日後の2月24日が高校の卒業式だった。
就職が決まった奴、進学が決まった奴、これから受験の奴、この日にクラスメイトの進路を確認しあうこともあった。
大きな声での会話や笑い声に満ち溢れて久々に楽しい気分になった。
友達同士で写真を撮りあった。何枚も撮った。
あまり喋ったことが無いような奴とも撮った。
「一生会わない奴がいっぱいいるんだろうな」
そんなことを考えながらなので沢山の同級生と写真を撮った。
「吉田君、写真撮ってくれる?」
話したことさえないような大人しい女子生徒が二人やってきた。
「ええよ。」
特になんてこともなくそう答えた。
彼女らは私を促して教室から少し離れたところに行った。
そこには酒田さんがいた。
みんなで撮るのではなくて酒田さんと二人での写真だった。
微妙に距離を置いてポケットに手を突っ込んでぎこちなく微笑む俺がいる。
ニコニコした笑顔の酒田さんがいる。
何十年も経った今でも家のどこかにそんな写真はあるはずだ。「これ、もらって。」
酒田さんから何かを渡された。
家に帰ってから開けてみるとチョコレートだった。
カードが添えてあった。
『10日遅れのチョコレートですが食べて下さい。』
お父さんが亡くなるってどんなにつらいんだろう。
そんなときも俺の事を考えていてくれたんだろうな。
そんな風に思うと胸が熱くなった。
恋に発展することは無かった。
お礼の電話をして一度だけ京都の嵐山に一緒に行った。高校の卒業式が2月24日でその日にこういう出来事があったことをよく覚えている。
竪琴を弾く白い服の女性
大阪の夏の夜は蒸し暑く毎日が寝苦しかった。網戸をつけた窓を開けて寝るが、蚊が入ってきたり、外の気配が聞こえてきて安眠出来ない夜が続く。嫌な夢をよく見た。
オリンピックの儀式に出て来るような白くヒラヒラとした服を着た美しい女性がポロンポロンと竪琴を弾いている。
私をじっと見つめて微かな微笑みを抱いている。
『この女性に引き込まれたらあの世に連れて行かれるんだろうな』
そんな気がしていた。
『これって現実ではなくてただの夢だ』
同時にそんな気もしていた。少しずつ目が覚めてくるのが判った。
『やっぱり夢だったんだ』
恐怖が薄らいできた。
しかし何故か竪琴の音が聞こえる。
目が覚めれば覚めるほどしっかりと聞こえる。
「ポロンポロン」
部屋の外のベランダの方から聞こえてくる。
『これって幽霊だな』
『あの夢は現実だった』
『目を開ければ絶対に幽霊がいる』
少し目を開けた。
夢に出て来た美しい女性が白いヒラヒラした服を着て竪琴を弾いている。
「ポロンポロン」
夢ではなくて現実の音が聞こえる。
『俺もいよいよ幽霊デビューだ。』
恐怖感はなかった。
『この美しい女性に連れて行かれてしまうんだろうか』
ぼんやりとそんな事を考えながら薄目を開けたり、目を閉じたりを繰り返した。
『まあ、それも良いか』
思い切って目をしっかりと開いた。窓に掛かるレースのカーテンが微かに揺れていた。そばに置いたクラシックギターにカーテンが触れるとポロンポロンと音が鳴っていた。幽霊デビューは持ち越しとなった。
ホッとしたというより残念だった。
連れて行かれても良かったかも?オリンピックの儀式の映像を見るとあの夏の夜を思い出す。
今日も見るかも知れない儀式に出て来る女性があの夜と同じ顔だったらちょっと嬉しい。